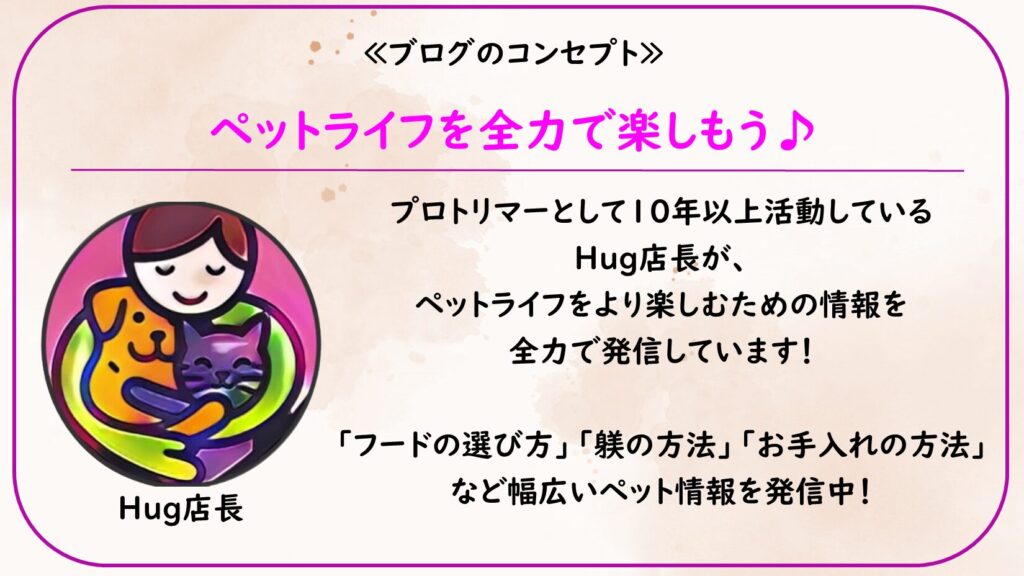
ペットとのお散歩やお出かけは気持ちもいいし、とても楽しい時間ですよね♪
しかし暖かい季節のお出かけはマダニに感染する危険性があります。
マダニはペットや人体の皮膚に寄生して吸血を行う虫ですが、時々危険なウイルスを保有してマダニから感染することがあります💦
ちゃんとした知識をもって行動することで、感染リスクを極力なくしたり、危険なウイルスの予防にも繋がります。
今回のブログでは
1.マダニの生態について
2.マダニから感染する病気
3.マダニから身を守る方法
4.マダニに寄生されたときの対処方法
について解説しておりますので、しっかり対策をして楽しいお出かけにしましょう(*^-^*)
1.マダニの生態について

一言でマダニといってもどんな虫なのか想像できない方もおられると思いますので、まずはマダニの生態や寄生される場所について学んでいきましょう!
①主な活動時期
マダニが活発に活動する温度は20℃~30℃くらいになると活発に活動を始めます。
季節としては夏から秋にかけて注意が必要です。
②マダニが潜んでいる場所
マダニは草むらに潜んでいることが多いです。
例えば、ペットとのお散歩で公園の草むらや河川敷の河原周辺などで遊んだりするとペットの体中にマダニがびっしり!
ということも珍しくありません。
③マダニの生涯のサイクル
マダニは吸血と脱皮を繰り返しながら成長と寄生を繰り返します。
大きくなったマダニは1~2cmくらいになるので見つけやすいですが、なるべく早く見つけられるようにマダニの生涯のサイクルについても学んでみましょう!
幼ダニ
体長:約1mm
最適な湿度化では20~30日間で卵から幼ダニがふ化して動物に寄生。3~7日間の吸血後、地表に落下し、次の発育期へと脱皮する。
若ダニ
体長:最大で約1.6mm
3~7日間の吸血後に地表に落下。脱皮1~2週間後には、新宿主に寄生できる状態となる。
成ダニ
体長:オス3~4mm、メス3~4mm
動物が通過する際に体熱や二酸化炭素、振動などを感知してすばやく乗り移る。約1~2週間かけて吸血する。
飽血したメスマダニ
飽血した(吸血でいっぱいに膨らんだ)メスマダニは、地上に落下して産卵を開始。2~3週間の間に2,000個~3,000個の卵を産み、その生涯を終える。
2.マダニが引き起こす病気や症状

①貧血
マダニから大量に寄生・吸血された際に貧血を引き起こします。
特にチワワやミニチュアピンシャーの様な超小型犬や生後間もない仔犬・子猫は貧血症状が命に係わることもあるので
寄生されない様に特に注意しましょう!
②アレルギー性皮膚炎
マダニの唾液がアレルゲンとなり、強いかゆみなどを引き起こします。
③ダニ麻痺症
マダニは種類によって唾液中に毒性物質を産生するものがいます。そうしたマダニに吸血され、毒性物質が体内に注入されると、神経障害(弛緩性麻痺)を引き起こします。
④バベシア症<バベシア原虫>

破壊された赤血球
犬の症状
貧血、発熱、黄疸、元気消失など。症状が重い場合は急死することも
人の症状
発熱、貧血など
⑤日本紅斑熱<リケッチア>
病原体は日本紅斑熱リケッチア、媒介ダニはマダニ類です。潜伏期間は2~8日で、症状は高熱、発疹、刺し口等で重症化し、死亡することがあります。主に西日本で発生が見られ、兵庫県内でも報告されています。
⑥ライム病<ボレリア菌>
犬の症状
発熱や食欲不振、全身性痙攣、関節炎など
人の症状
赤い丘疹(マダニに咬まれた部分を中心とする遊走性紅斑)や発熱、関節痛など。放置すると、心膜炎や顔面神経麻痺などが起こることも
⑦Q熱<コクシエラ菌>
 提供/北里研究所 生物製剤研究所 小宮智義先生
提供/北里研究所 生物製剤研究所 小宮智義先生
犬の症状
不顕性感染(軽い発熱や流産・不妊症などが見られる程度)
人の症状
インフルエンザに似た高熱や呼吸器症状、肺炎など。慢性の場合は疲労感、慢性肝炎、心筋炎など。うつ病などの精神的な疾患と間違われることも
⑧エールリヒア症<リケッチア>
犬の症状
急性の場合は発熱、鼻汁、流涙、食欲不振、元気消失、貧血など
人の症状
発熱、頭痛、関節痛、倦怠感、呼吸困難など。放置すると、命に関わることも
⑨重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)
ダニに刺されてから6日~2週間程度で、原因不明の発熱、消化器症状(食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛)が中心です。時に頭痛、筋肉痛、神経症状(意識障害、けいれん、昏睡)、リンパ節腫脹、呼吸器症状(咳など)、出血症状(紫斑、下血)など様々な症状を引き起こします。重症化し、死亡することもあります。
3.マダニから身を守る予防方法

マダニに寄生された時のリスクについて学んだ後は、マダニに寄生されないための予防方法について学んでいきましょう!
①ペットの予防方法
ペットに寄生したマダニが、屋内で成長して飼い主さんに寄生することもあるので、なるべくペットに寄生しない様に気を付けましょう。
予防方法1 草むらに入れない
マダニは主に草むらの中に潜んでいます。
ペットと一緒にお出かけする時は草むらの中に入れない様に徹底しましょう。
予防方法2 動物病院で予防の薬を処方してもらう
動物病院では『フロントライン プラス』という滴下タイプの予防薬を処方してもらえます。
フロントラインは液状タイプの薬剤になっており、身体に滴下することで効果を発揮します。
滴下された薬剤は毛穴を通じて皮脂腺へと吸収され、ゆっくりと皮膚へと効果を発揮します。
滴下後24時間で皮脂腺へと吸収されるので、それ以降はシャンプーを行っても効果が持続します。
ホームセンターで販売されているものは、病院で処方されているものとは薬剤が違いシャンプーをすると効果を失ってしまうので、なるべく動物病院で処方してもらいましょう。
②人間(飼い主)の予防方法
人間の場合も草むらや藪などマダニが多く生息する場所に入る場合には、長袖・長ズボン(シャツの裾はズボンの中に、ズボンの裾は靴下や長靴の中に入れる、または登山用スパッツを着用する)など皮膚が露にならないような工夫が必要です。
足を完全に覆う靴(スニーカーや長靴など)を着用し、上から落ちてこないように帽子や、首にタオルを巻く等、肌の露出を少なくすることが大事です。

参照:国立健康危機管理研究機構
服は明るい色のもの(マダニは身体が黒いため、明るい服装だと目視で確認しやすい)がお薦めです。
虫除け剤の中には服の上から用いるタイプがあり、補助的な効果があると言われています。
厚生労働省でも啓蒙のポスターが作られるほど注意喚起されていますので、ペット共々、しっかり予防対策を取っていきましょう!
【厚生労働省ホームページ】
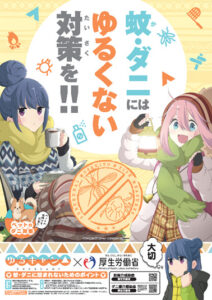
4.マダニに寄生されたときの対処方法

マダニに対しては予防を心がけるのが大切ですが、もしマダニに噛まれているのを気づいた時の対処方法についても学んでいきましょう!
①ペットに寄生した場合
もしペットにマダニが寄生しているのに気づいた時はちゃんとした方法で対処しないと二次被害を引き起こしたり、悪化する場合もありますので自分で取ることはしないで、動物病院で治療してもらうのがおススメです!
※少量のマダニであれば、トリマーさんが対応することも可能なので場合によっては相談してみましょう。
マダニに気づいた時にやってはいけないこと
①自分で取る
ピンセットで取れることもありますが、マダニの構造上、口先の吸血している部分が皮膚に食い込んでいることが多いのです。
取り方を間違うと、マダニの顎先が皮膚に残ってしまうことがあります。
マダニの顎先が皮膚に残ってしまうと皮膚炎や感染症により化膿することがあるので、なるべく病院で処置をしてもらいましょう。
②マダニを潰す
マダニにもオスとメスがあるのですが、見た目では判別が出来ません。
もし成長したメスのマダニを潰してしまうとマダニの卵が大量に散乱してしまうことになるので、もしマダニが室内に落ちていたら潰したりせずにピンセットなどで拾い上げて
●ハイターで溶かす
●トイレに流す
と良いと思います。
ごみ箱に捨ててしまうと、ゴミ箱から這い出てしまうことがあるので、しっかりと処理をしましょう。
②人間(飼い主)に寄生した場合

屋外活動で草むらや藪の中で活動した場合は、身体にマダニがついていないかチェックをしていきましょう!
マダニへの対処方法
屋外活動後は入浴し、マダニに咬まれていないか確認して下さい。
特に、わきの下、足の付け根、手首、膝の裏、胸の下、頭部(髪の毛の中)などがポイントです。
もしマダニを見かけたら、ピンセットで食いついている根元(マダニの頭部)をつまんでゆっくり引きはがすことができます。
自信がない場合は決して引っ張らず病院で治療してもらうと良いと思います。
簡易的に試せる方法としては、シャワーをかけたり、湯船に入ることで離れる事があるのでまずは入浴して対応してみましょう。
お風呂上りにもまだ取れない時は、ワセリンをマダニの部分に塗ることで呼吸が出来ずに取れることもあります。
マダニに噛まれた後にやってはいけないこと
①自分で無理やり剥がす
マダニの吸血器官は皮膚に食い込むことがあるので、無理やりに取るのではなく、入浴やワセリンで対処しましょう。
もしくは、皮膚科で対応してもらうことが最善の手段になります。
②体調不良を放置する
マダニは危険が病原菌を持っていることがあるので、体調が悪くなった時はすぐに病院で受診しましょう!
特に最近は、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)という命に関わるウイルスを保有していることもありますので、発熱や倦怠感がある時は、すぐに病院で受診しましょう!
放置すると命に関わるということを常に意識しましょう!
5.まとめ

マダニはただ吸血するだけの寄生虫ではなく、危険なウイルスや病原体を保有していることがあるので、命を守るためにも、しっかり対策をとりましょう。
具体的には
●草むらに入らない(ペットも)
●噛まれたときは病院で処置してもらう
●具合が悪くなったらすぐに受診する
ということに気を付けて過ごしましょう。
X(Twitter)やInstagramでもブログの更新のお知らせや、情報発信をしていますので良ければフォローやリポストしてもらえたら嬉しいです♪(*‘ω‘ *)
これからも皆さんのペットライフが楽しくなる情報発信を続けてまります!
・ペットライフの充実
・ペットに関する話題のネタ
・子どもとの会話のきっかけ etc...
として役立てたら嬉しいです!ぜひ次の投稿もご期待ください(^^♪

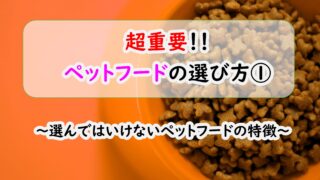










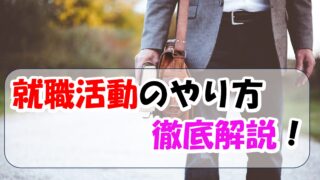
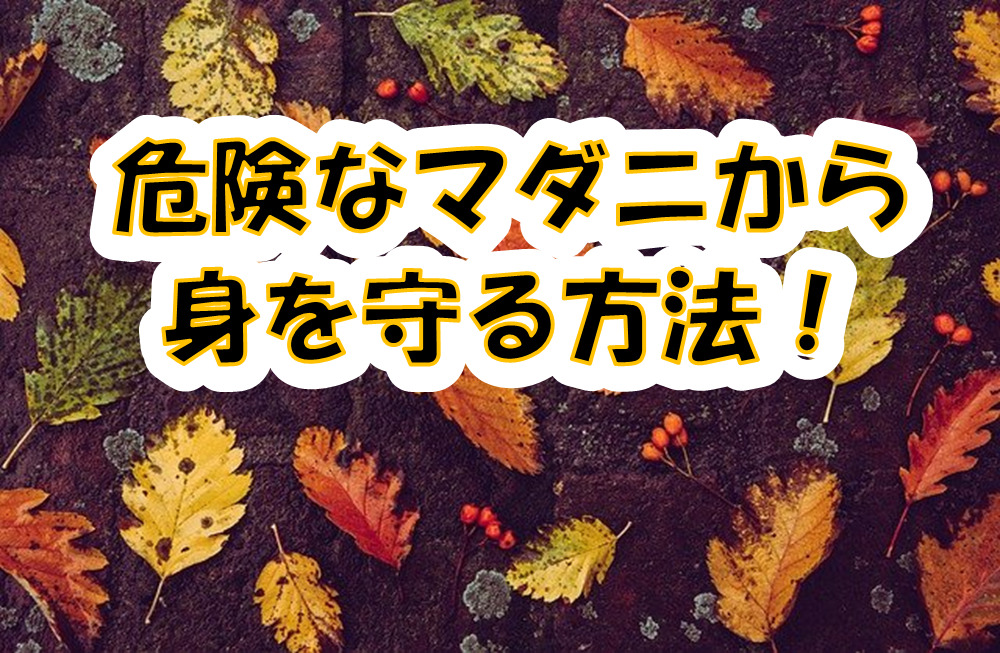





コメント