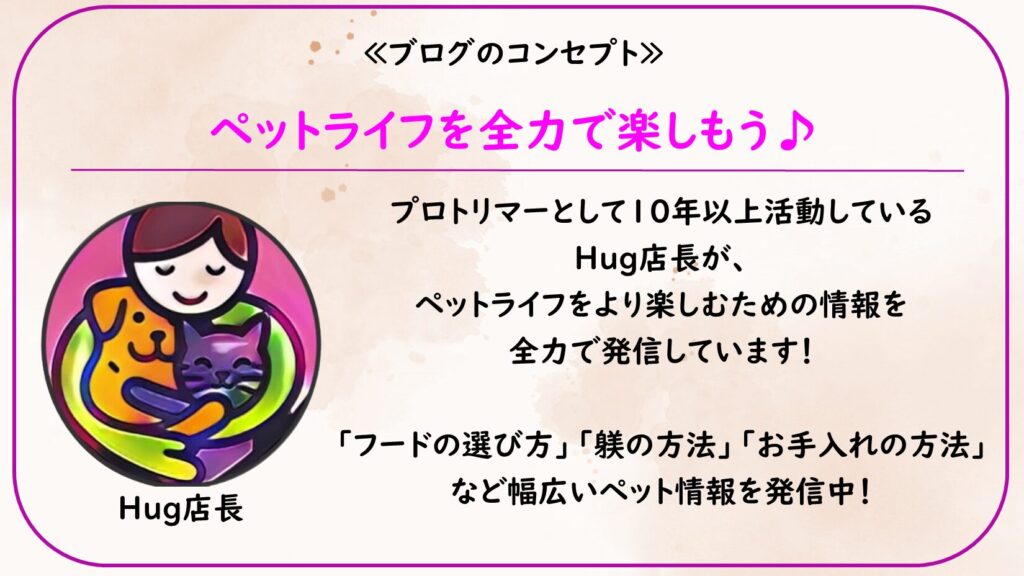
プロトリマー10年以上の『Hug店長』です!
今回は【初心者必見!失敗しないペットフードの選び方】を解説します♪
ペットは大切な家族の一員!だからこそ、毎日口にするフードは慎重に選びたいものです。
ですが、ペットショップやネットには種類が多すぎて、
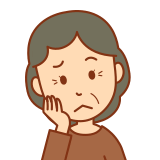
どれを選べばいいの?💦
と悩んでしまいますよね?
食事は身体や健康を維持するためにとても重要です!
ペットフードを選ぶ時に、『自分のペットに合わないフード』を選んでしまうと、健康を守るどころか、皮膚炎や外耳炎などアレルギー症状が起こる原因になりかねません💦
今回のブログでは、ペットフードを選ぶ際にどういった点を見て選べば良いのか、飼い主さんにもわかりやすく、ポイントを押さえた選び方をご紹介します。
食事は身体を作る基礎になるものなので健康を維持したり、健康を維持することで病気を予防にも繋がります。
ペットフードの特徴をしっかり学んで、ペットの健康を守ってあげましょう!
1. ペットフードの種類を知ろう

まずはペットフードの基本的な種類を把握しましょう。
ペットフードはその形状や、ペットフードに含まれる水分量によって種類が異なります。
ドライフード(カリカリ)
≪特徴≫
-
水分含有量:約10%以下
⇒水分量が少ないので腐敗しにくく長期保存しやすい -
粒状で乾燥しており、保存性が高い
-
密封容器に入れれば数週間~数カ月保存可能
≪メリット≫
-
経済的:同じ栄養量でもウェットより安価
-
歯の健康に◎:噛むことで歯垢が付きにくくなる
-
計量しやすい:カロリー管理がしやすい
-
常温保存できるので、まとめ買いが可能
≪デメリット・注意点≫
-
香りが少ないため、食欲が落ちている子には不向き
-
水分がほぼないため、別途水分補給が必要
-
歯の弱い高齢ペットには硬すぎる場合がある
- 小型犬種が喉に詰まらせないように粒のサイズに注意が必要
セミモイストタイプ
≪特徴≫
-
水分含有量:約25~35%
-
柔らかめで噛みやすく、香りも比較的強い
-
袋入りやトレー入りなど形状はさまざま
≪メリット≫
-
食べやすさ◎:歯の弱い子や子犬・子猫に適している
-
嗜好性が高い:香りや食感がウェットに近く、食欲促進に役立つ
-
開封後も短期間なら冷蔵なしで保存できるものもある
≪デメリット・注意点≫
-
保存期間はドライより短く、開封後は数日で食べ切りが必要
-
加工過程で砂糖や塩分、保存料が多く使われている製品もある
-
種類が少なく、総合栄養食ではなく間食用(おやつ扱い)の商品も多い
ウェットフード(缶詰・パウチ)
≪特徴≫
-
水分含有量:約75%前後
-
缶詰、アルミトレイ、パウチ入りなど形態が豊富
-
柔らかく、香りが強く、嗜好性が高い
≪メリット≫
-
食いつき抜群:香りや食感が良く、好き嫌いが多い子にも向く
-
水分補給に役立つ:腎臓病予防や泌尿器ケアに有効
-
消化しやすく、歯や顎が弱い高齢ペットにも食べやすい
≪デメリット・注意点≫
-
開封後は冷蔵保存が必要(1~2日以内に食べ切る)
-
ドライに比べて価格が高く、長期的にはコスト増
-
歯石予防効果はほとんどないため、別途デンタルケアが必要
2.原材料の表示ルール(日本の場合)

-
使用量の多い順に記載
ペットフードに記載されている『原材料』の欄は、「食品表示法」という法律に基づいて、使用されている原料が多い順に記載されています。
一番最初に書かれている原料が、そのフードに最も多く含まれている材料です。
例)「鶏肉、米、トウモロコシ、魚粉…」とあれば、鶏肉が主原料。 -
加工前の状態での重量順
水分を含んだ状態で計算されるため、肉類や野菜は見かけ上順位が上がりやすい。 -
すべての原料を記載
主原料だけでなく、ビタミンやミネラル、保存料などの添加物も含めて表示されます。
3.「原材料」と「成分表示」の違い

原材料とは?
- 成分表示:そのフードに含まれる栄養の割合
(例:粗たんぱく質25%、粗脂肪12%、水分10%)
-
フードを作るために使われた「素材の一覧」
-
使用量の多い順に記載(法律で義務付けられています)
-
加工前の状態で計算されるため、水分が多い肉や野菜は表示上の順位が上がりやすい
👉 「何から作られているフードか」を知るために確認する項目です。
成分表示とは?
-
そのフードに含まれる 栄養素の割合(分析値) を示したもの
-
主に「保証成分値(Guaranteed Analysis)」として表記されます
-
栄養バランスをチェックするために重要
例:
粗たんぱく質 26%以上
粗脂肪 12%以上
粗繊維 5%以下
灰分 8%以下
水分 10%以下
👉 「どんな栄養バランスになっているか」を知るために確認する項目です。
原材料と成分表示の違いまとめ
| 項目 | 原材料 | 成分表示 |
| 内容 | 何を使って作っているか(素材一覧) | その結果どんな栄養素がどれくらい含まれているか |
| 表示順 | 使用量が多い順 | 栄養素ごとに規定値(%) |
| 確認ポイント | 肉や魚が主原料か、穀物の割合、添加物の有無 | たんぱく質や脂質が十分か、カロリーや水分量 |
| 意味 | 「材料の質」を見る | 「栄養バランス」を見る |
飼い主さんへのアドバイス
-
原材料表示 → 「素材の質」をチェック
→ 肉や魚が主原料になっているかを確認 -
成分表示 → 「栄養バランス」をチェック
→ 愛犬・愛猫のライフステージや体質に合っているかを判断
この両方を組み合わせて見ていくことで、本当に良いフードを選ぶことができます。
4.良いペットフードの見分け方

ペットフードは価格だけで選ばず、ペットフードの原材料を確認することが大切です。
以下のポイントをチェックしましょう。
4-1. 主原料が「肉」かどうか
ラベルの最初に「チキン」「ビーフ」「サーモン」など、動物性たんぱく質が記載されているものを選びましょう。
4-2. 添加物の少なさ
人工保存料、着色料、香料などが少ない、または無添加のフードを選ぶのが理想的。アレルギーや体調不良の原因になることも。
4-3. AAFCOやFEDIAFの基準を満たしているか
栄養バランスが整っているかをチェックするには、「総合栄養食」と表示されているかを確認しましょう。
①総合栄養食の定義
-
犬や猫のライフステージ(成長期、成犬期、シニア期など)ごとに必要な栄養素(たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラルなど)がすべて含まれている。
-
AAFCO(米国)やFEDIAF(欧州)などの国際基準、または日本の「ペットフード公正取引協議会」の基準を満たしている。
-
主食として長期間与えても、栄養不足や過剰にならないよう設計されている。
②総合栄養食とその他の分類の違い
| 種類 | 役割 | 特徴 |
|---|---|---|
| 総合栄養食 | 主食 | 栄養バランスが整っており、水と一緒に与えればOK |
| 間食(おやつ) | 補助 | 嗜好性重視。栄養バランスは考慮されていない |
| 療法食 | 医療補助 | 特定の病気や症状に合わせて栄養成分を調整(必ず獣医師の指導で使用) |
| 一般食・副食 | 補助 | 総合栄養食と一緒に与えることを前提にした食品 |
③飼い主さんが確認すべきポイント
-
パッケージ表示を確認
「総合栄養食」と明記されているかどうか。 -
ライフステージに合っているか
子犬用・成犬用・シニア用など、対象年齢を確認。 -
基準に準拠しているか
「AAFCO基準適合」や「FEDIAF準拠」などの表記があると安心。
4-4. ペットの年齢や体質に合っているか
・子犬/子猫:成長に必要な栄養が多め
・成犬/成猫:体重管理や健康維持が中心
・シニア:消化しやすく、カロリー控えめ
4-5.穀物が多く使用されているフードを選ばない
ペットフードの原材料ラベルを見たとき、最初に「トウモロコシ」「小麦」「米」など穀物がずらっと並んでいませんか?
これは原料の中で穀物が最も多く使われていることを意味します。
一見ヘルシーに感じるかもしれませんが、犬や猫にとっては必ずしも理想的ではありません。
穀物が多く使用されているペットフードを使用するデメリットとしては以下の4つがあげられます。
①動物性たんぱく質の不足につながる
犬は雑食寄り、猫は完全肉食動物です。
しかし、穀物が主体のフードは動物性たんぱく質が少なくなり、筋肉や臓器、被毛の健康維持に必要な栄養が不足する恐れがあります。
②消化しにくい
犬や猫は、人間ほど穀物の消化に向いた消化酵素(アミラーゼ)を持っていません。
特に猫は穀物を効率的に分解できず、消化不良や便の質の悪化を招くことがあります。
③アレルギーや皮膚トラブルの原因になりやすい
小麦やトウモロコシは、犬や猫の食物アレルギーの原因になりやすい原料です。
皮膚のかゆみ、耳の炎症、涙やけ、下痢などの症状が出る子もいます。
④カロリー過多による肥満リスク
穀物は炭水化物が豊富で、過剰に摂取すると肥満につながります。
特に運動量が少ない室内飼いの犬や猫には、体重管理の面で不利です。
5.ペットの個性に合わせた選び方

動物種や犬種、性格、体調によってもベストなフードは異なります。
-
アレルギーがある子には…
グレインフリー(穀物不使用)のペットフードや特定のたんぱく源に限定したフードを。 -
食べムラがある子には…
嗜好性の高いウェットフードやトッピングも検討。 -
体重が気になる子には…
ローカロリータイプや肥満対策用を選びましょう。
6.犬のフードを選ぶときの注意ポイント

-
タンパク質の質と量
犬は雑食寄りですが、良質なたんぱく質が必須。特に活動量が多い犬は高たんぱくフードが向きます。 -
関節ケア成分の有無
大型犬や老犬には、グルコサミン・コンドロイチン入りがおすすめ。 -
穀物アレルギーの可能性
皮膚がかゆい(外耳炎・皮膚炎など)、下痢しやすい犬はグレインフリー(穀物不使用)も検討。 -
体重管理
肥満は関節や心臓に負担をかけます。活動量に応じたカロリー設定を。
7. 猫のフードを選ぶときの注意ポイント

-
動物性たんぱく質が必須
猫は完全肉食動物。主原料が肉や魚のものを選びましょう。 -
水分補給の工夫
猫はあまり水を飲まないため、ウェットフードやスープタイプを併用すると腎臓病予防にもつながります。 -
タウリンの含有量
猫にとって必須アミノ酸となる『タウリン』が不足すると、失明や心臓病の原因になるため、必ず含まれているか確認。
ペットフードに総合栄養食と記載されていれば大丈夫です! -
尿路結石の予防
マグネシウム量や尿pHの調整に配慮されたフードがおすすめ。
まとめ:試して調整する姿勢が大事

今回は「ペットフードの形状や特徴」と「ペットフードの選び方」についてまとめさせて頂きました。
ペットフードはその形状やメーカーによって、特徴やメリットが違います。
そうした様々なペットフードの中から自分たちの愛犬・愛猫に合ったペットフードを選ぶためには、原材料や成分を見ながら選ぶ必要があります。
また、どれだけ良さそうに見えるフードでも、実際にペットが食べてくれなければ意味がありません。
特に初めて使用するフードは少量パックで試してみるのがおススメです。
愛犬・愛猫に合った食事を見つけるまで少し時間がかかるかもしれませんが、「元気」「便の状態」「毛づや」などを観察しながら、最適なフードを見つけていきましょう。

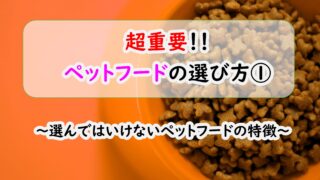







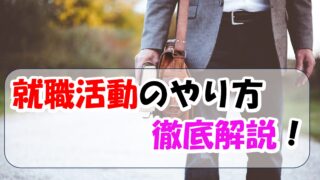



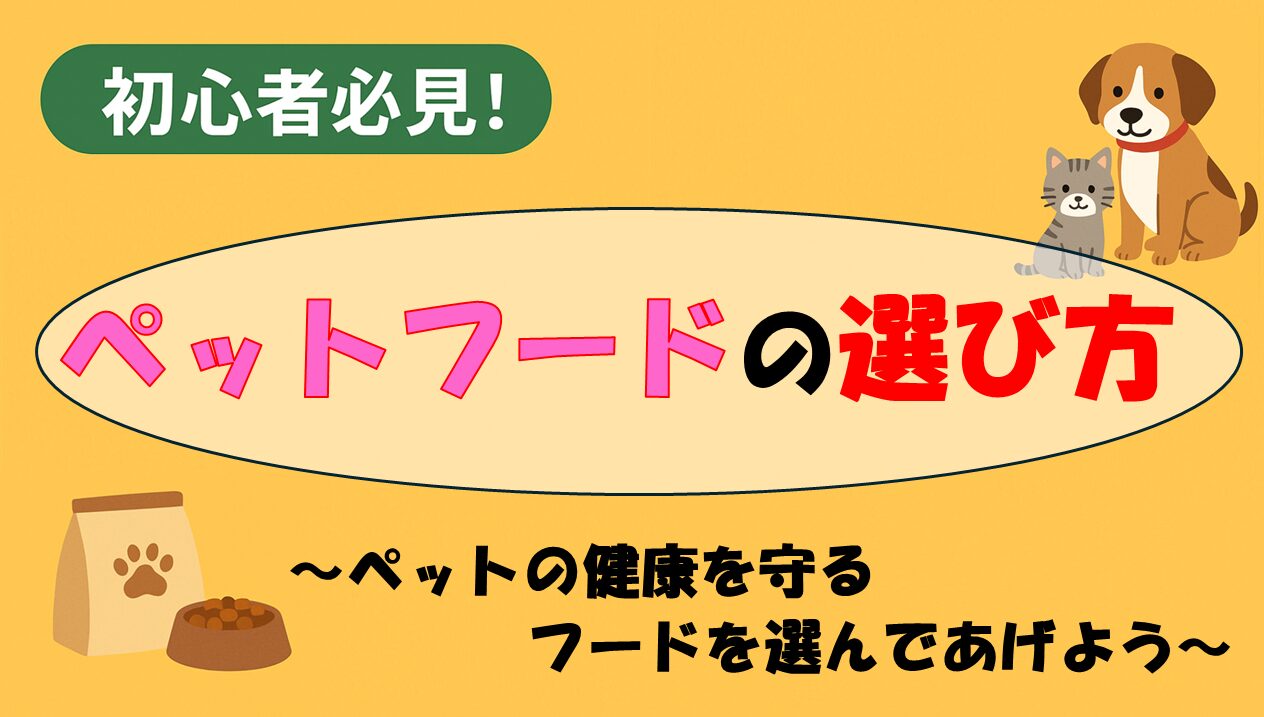


コメント